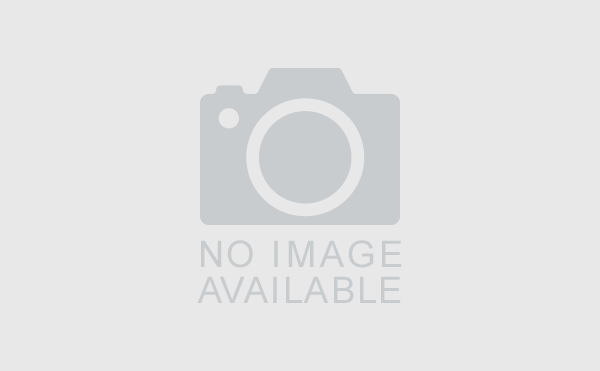コロンビア・カリ近郊で芽吹くカカオ新潮流 ― 日本市場とラム酒の可能性

今年の一時帰国の際に、「日本向けにカカオを輸出したい」と思いに火がつきました。それも、イバゲやサンタンデールではなくて、このカリ付近で。もちろん、南西部のバジェ・デル・カウカ県はまだ新興地であることはわかっているけれど、以前からずっと高品質なカカオづくりを目指す生産者が増えていることは聞き及んでいたし、農業投資家や食品加工業者から「次の成長産業」として期待されつつあるのです。

(カリはここです)
1.高品質市場を狙うカリの農家
この地域は、サトウキビやコーヒーと並んで農業基盤が強い。もともと多様な作物栽培に適した肥沃な土地を持つため、カカオ栽培に転じる生産者が増えているそう。
近年では、国際市場で需要が拡大する「フィノ・デ・アロマ(Fino de Aroma)」と呼ばれる高品質カカオの生産が注目されていますよね。日本でもチョコレートの高級化が進み、原料段階での品質やストーリー性を重視する傾向が強まっているのは見ての通り。産地のトレーサビリティや農家の顔が見える原料調達は、日本のクラフトチョコレートメーカーや菓子企業にとって魅力的な要素だ。カリ近郊のカカオはまだ輸出量が少なく、「新しいブランドストーリー」を探す日本企業にとって掘り出し物となる可能性があるのでは、と勝手に思っています。
2.課題と可能性 ― 日本への輸出は?
もっとも、コロンビアから日本へのカカオビーンズ輸出は、物流・品質管理・規模の三つの課題がありそう。まず、コロンビアからの直行便が少なく、コンテナ輸送のコストが高い。さらに、日本の食品衛生法や農薬残留基準に適合させるには、生産段階での厳密な管理が必要だ。規模についても、カリ近郊は小規模農家が中心で、安定供給には生産者団体の協力や契約栽培の仕組みづくりが不可欠となります。しかし、このハードルは裏を返せば①数量よりも品質・ストーリー・希少性を重視する消費者の期待にこたえられる、②少量でもユニークなカカオを届けられれば十分に競争力を持つ(たとえば、単一農園のカカオをそのまま輸出し、「カリ近郊発のシングルオリジン」として日本でブランド展開すれば、産地の知名度を高めながら付加価値を生み出せる)。
3.ラム酒とのかけ合わせ ― 食文化の新しい可能性
さらに目論んでいるのは、カリ近郊のカカオとカリブ海文化圏を象徴するラム酒との融合。コロンビアでもカリブ沿岸地域を中心にラム酒生産(!)が盛んだが、近年はカクテル需要の高まりからプレミアムラムも注目です。
チョコレートとラム酒の相性は抜群なので、例えば奄美産ラムとカリ近郊のカカオを組み合わせれば、「原産国同士のストーリーあるペアリング」として新たな商品カテゴリーを生み出せます。日本でもウイスキーや日本酒とのペアリング文化が浸透しつつあり、その延長線上で「ラム×カカオ」の組み合わせは面白い挑戦になるだろう。たとえば、ラム酒に漬け込んだカカオ豆や、カカオニブを使ったラムボンボンといった商品は、バレンタインや高級バー市場に適した新商材となるかもしれません。
4.AKARI SASで着手することは?
カリ近郊でのカカオ生産はまだ発展途上にあります。しかし、持続可能性や高品質志向といった世界的な潮流、そして日本市場におけるクラフト・プレミアム志向の高まりは、この地域の農家にとって大きな追い風。さらに、日本産ラム酒や他の地域資源と掛け合わせることで、単なる一次産品輸出にとどまらない新たな付加価値を創出できる。
今はまだ萌芽といえる「カカオの新しい物語」ですが、早速地場カカオ協会にコンタクトをとり、面白い生産業者の選定にあたっています(この、おいしいか希少性があるか、ではなくて、おもしろいか否かで判断するのが弊社らしい。迷ったらアホな方を選択する社長なのです)。輸出への挑戦は簡単ではありませんが、少量高品質・ストーリー性・他産品とのペアリングといった切り口で攻めれば、日本とコロンビアを結ぶ新しいビジネスの芽が育つと、私は確信しています。乞うご期待!