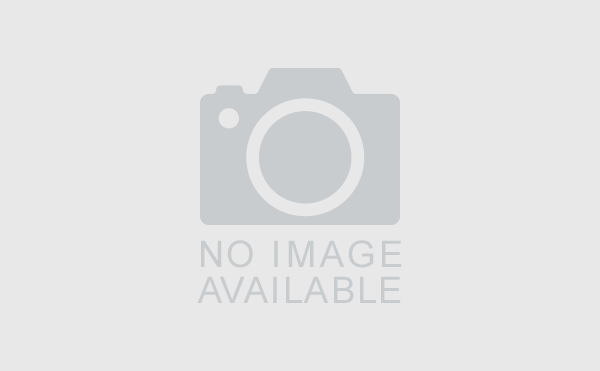コロンビア、次の成長戦略は「機会作物」──ピーチパームとチャヨーテに光を
コロンビア政府がいま注目しているのは、コーヒーでもカカオでもありません。新たな農業戦略のキーワードは「機会作物(opportunity crops)」です。その先頭に立つのが、ハヤトウリ(Bactris gasipaes)とチョンタドゥーロ(Sechium edule)の2つの作物です。どちらも一般にはあまり知られていませんが、将来性の高さから“次の主役候補”として大きな注目を集めています。

ハヤトウリ

チョンタドゥーロ
チョンタドゥーロはアマゾン原産のヤシ科植物で、果実は赤やオレンジ色を帯びた丸い実をつけます。その味は栗やカボチャに似ており、南米ではゆでて塩をふり、軽食として親しまれてきました。栄養価が非常に高く、「森のスーパーフード」とも呼ばれます。一方のハヤトウリはウリ科のつる性植物で、緑色の洋ナシのような外見をしています。日本では「隼人瓜(はやとうり)」として知られ、シャキッとした食感が特徴です。
この2つの作物が注目される背景には、コロンビア農業省と国際作物多様性機関(Crop Trust)による共同プロジェクトがあります。目的は、農業の多様化と気候変動への適応力(レジリエンス)の強化です。
コロンビアの農業はこれまで、コーヒー、バナナ、花卉といった主要輸出品目に依存してきました。しかし近年、異常気象の増加や国際市場の価格変動によって、農家の収益が不安定化しています。こうした状況を受け、政府はより多様な作物への転換を進めています。その中核をなすのが「機会作物」戦略です。
Crop Trustは、世界各国で作物の遺伝的多様性を保護する国際機関です。同機関は、各国が自国固有の作物を見直し、地域資源として再開発することを提案しています。コロンビアでは2025年、候補作物48種の中からチョンタドゥーロとハヤトウリが選定されました。どちらも栄養価が高く、気候変動に強く、加工・輸出の潜在力を持っている点が評価されたのです。
チョンタドゥーロの果実は、たんぱく質・βカロテン・鉄分が豊富で、地元ではゆでたり、ペーストにしてスープやスナックに利用されています。さらに搾油も可能で、赤みを帯びたオイルは抗酸化成分を多く含み、健康志向の高い市場で「プレミアム植物油」として注目されています。南部プトゥマヨ県では、すでに地元農家が小規模な加工施設を整備し、チョンタドゥーロオイルを首都ボゴタやメデジンの健康食品店に出荷し始めています。
一方、ハヤトウリは成長が早く、病害虫にも強い作物です。標高1,000〜2,000メートルの山間地でもよく育つため、気候変動の影響でトウモロコシや豆の収穫が不安定な地域では、代替作物として期待されています。アンティオキア県では、農協と大学が連携し、ハヤトウリの冷凍加工やピクルス製品の試作を行っています。アジア市場、とりわけ日本や韓国での健康志向を意識した取り組みが進行中です。
コロンビア政府はこれらの取り組みを実験的な試みではなく、国家レベルの成長戦略として位置づけています。農業省の計画によると、2026年までに10県でパイロット事業を展開し、生産・加工・輸出の一貫体制を構築する方針です。また、作物ごとの最適地域マップを作成し、農家への技術支援や資金援助も拡充する予定です。これは、いわば「コロンビア版・次世代フードバリューチェーン」の形成といえます。
もちろん課題も残っています。チョンタドゥーロは幹に鋭い棘があり、収穫作業が難しくコストが上がりやすいのが難点です。ハヤトウリは鮮度が落ちやすいため、コールドチェーン(低温物流)の整備が欠かせません。また、どちらの作物も大規模商業栽培の経験が浅く、収穫から加工・流通までのノウハウを蓄積する必要があります。
それでも、専門家の間では「挑戦する価値がある」という見方が広がっています。農業研究機関Agrosaviaの経済学者マリア・エスコバル氏は、「チョンタドゥーロとハヤトウリは単なるニッチ作物ではなく、地域経済の新しい柱になり得る。特に女性農家や若者の参入が進めば、地方経済の再生につながる」と語ります。
世界では、かつて“忘れられた作物”だったキヌアやアマランサス、モリンガなどが再評価され、国際市場で成功を収めています。チョンタドゥーロとハヤトウリもその流れに続く可能性があります。
気候変動に揺れる21世紀の農業において、真に強い作物とは「頑丈なもの」ではなく、「しぶとく生き延びるもの」です。チョンタドゥーロの鋭い棘も、ハヤトウリのしなやかなつるも、そのしたたかさの象徴といえるでしょう。コロンビアがこの2つの作物でどこまで世界市場を驚かせるのか、今後の展開が注目されています。