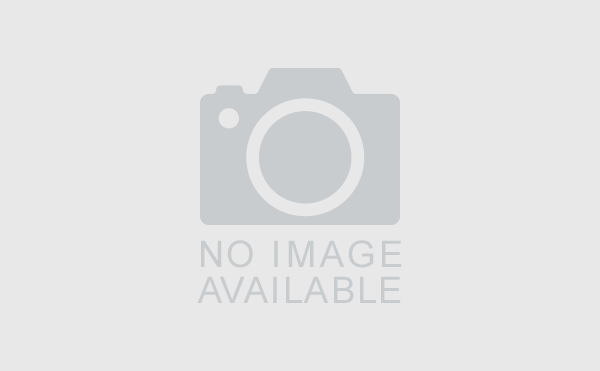コロンビア産パーム油、インド市場に急接近~「価格」と「持続可能性」の二枚看板はどうでるか~

お久しぶりです。約2か月の一時帰国を経てカリに戻りました。エアカナダは飛ばないし、滞在中ウェブサイトが不具合が起きたりと漫画のような日々でしたが今やっとほっとしてます。そして戻った途端野菜やら果物の差し入れの多いこと・・・。いつものことですがカリは皆さん温かい。心底支えられています。
私がコロンビアで生活を始めた15年前(!)は、こちらに住んでいるというだけで変人扱いでしたが、今回は「うらやましい」と言われることが多かったな。ギャング3人いてひいひい言ってるのに。海外に拠点をおいていることについて話を聞かせてほしいという声も増え、日本も変わってきた印象です。いつまでいるのとよく聞かれるけど、それは神様が決めると思ってます。必死で努力してれば、私の思う自分なりの幸せは獲得できると信じているので。
さて、ビジネスですが2025年8月、コロンビアのパーム油産業に新たな追い風が吹いています。インドの輸入業者が従来の大手供給国であるインドネシアやマレーシアではなく、コロンビアを筆頭にグアテマラ等中南米諸国から割安なパーム油を大量に購入した事実が発覚。その理由は価格の安さで、しかもインドで食用油需要が爆発的に増える秋のシーズン直前です。
☆1トンあたり約10ドル安価な中南米パーム油
数字だけ見れば些細に思えますが、インドの年間輸入量は数百万トン規模。わずか10ドルの差が最終的には数千万ドルのコスト削減につながることとコスト重視のインド市場で“新しいサプライヤー”を歓迎する十分な理由になった模様。
コロンビアは南米最大のパーム油生産国であり、世界第4位の規模を誇ります。これまで主な売り先はヨーロッパや米国で、「アジア市場に食い込むのは難しい」とされてきました(インドネシアとマレーシアが地理的・物流的な優位性を握り、価格でも圧倒的に有利だったから)。
しかし近年、コロンビアの状況は変化。まず港湾インフラの改善や物流効率化によって長年の課題だった輸送コストが低下。さらに、労働コストの安定や政府の農業支援政策もあり、輸出先を広げる余力が出てきたこと。そこに今回の「インドシフト」が重なったのは、輸出先の多角化を狙うコロンビアにとって、インドはまさに“狙い目”だったと言えます。
☆価格だけではない「付加価値」
単に安いから売れる、というわけではありません。むしろ今後の競争のカギを握るのは、コロンビアが打ち出す「持続可能性」の物語。ご存じの通り、パーム油は世界で最も消費されている植物性油ですが、同時に森林破壊や生物多様性喪失の象徴として批判の的にもなってきました。特にインドネシア・マレーシアの大規模農園開発は国際的な環境団体からの厳しい視線にさらされているとか。
その点、コロンビアのパーム油は「比較的クリーン」なイメージを打ち出しやすいのかもしれません。生産規模がアジアほど巨大ではなく、森林伐採の問題が比較的軽微。加えて、RSPO(持続可能なパーム油の円卓会議)認証を取得する農園も増加しており、「環境に優しいパーム油」として差別化を図れる余地がありそう。
つまり、①価格で入り込み、②持続可能性でポジションを固める。これがコロンビアの戦略となっています。
☆インド市場がもつ“魔力”
なぜインドに輸出するのか。それはインドが「世界最大のパーム油輸入国」であることに尽きます。人口14億人を超える超大国で、料理文化的にも揚げ物やスパイス料理に油を大量に使う。国内の油需要の半分以上を輸入に依存しており、特にパーム油は圧倒的なシェアを持っています。さらに、インドの食文化には“季節需要”があり、9月から始まる祭事シーズンには、菓子類や揚げ物の需要が一気に膨らむんだとか。油の価格はインフレと直結するため政府も国民も「安い油」を常に歓迎します。ここに、コロンビア産パーム油が割って入る余地が広がっているといえましょう。
☆ビジネスチャンスとリスク
もちろん、バラ色の未来だけではなく、解決すべき障壁もあります。まず、輸送コストのリスク。南米からインドまでの距離は長く、原油価格の変動は直撃。また、価格競争は常に激しく、アジア勢が値下げで対抗すれば一気にシェアを失う可能性もあります。
さらに、環境面の「優等生イメージ」も過信は禁物です。もし大規模拡張に伴い森林伐採が進めば、アジアと同じ批判の矢面に立つことになることは明らか。持続可能性をどこまで本気で実行できるか、それが長期的な勝敗を分けるといえそうです。
とはいえ、今回のインド進出はコロンビアにとって“開かれた扉”です。輸出市場の多角化は、農業国コロンビアが外貨を稼ぐ上で重要な生命線。パーム油は単なる農産物ではなく、国家戦略に関わる産業になりつつあります。となると、次の一手は「物語」づくりではないでしょうか?「安いから」だけで終わらせず、「アンデスの豊かな自然から生まれた、持続可能なパーム油」、「消費者も地球も満足させる新しい選択肢」。そんなブランドストーリーを編み出せるかどうかで、単なる一時的な輸出ブームか、長期的な市場ポジション確立かが決まります。
コロンビアのパーム油が単なる商品から“戦略的資産”へと進化することができるのか? 価格と持続可能性、二つの武器をどう磨くかに注目です。