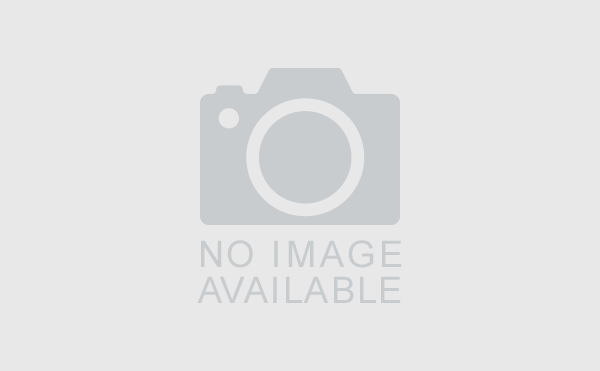コロンビアで始まる、「種をめぐる戦い」について

コロンビアの田舎町ナリーニョで、農家たちが小さなトウモロコシ畑を守ろうと立ち上がっています。彼らが守っているのは、何世代にもわたって受け継がれてきた“在来種の種(たね)”。一方で、国の政策や大企業は「もっと早く、もっとたくさん収穫できる」遺伝子組換え(GM)作物の導入を進めています。
この“種をめぐる戦い”が、いまコロンビアの農業界を揺るがせているのは一体なぜなのか?
コロンビア南部、ナリーニョやカウカといった山岳地帯では、「ガーディアネス・デ・ラス・セミージャス(種の守り人)」と呼ばれる農民たちがいます。彼らは自分たちの畑で育てた在来種のトウモロコシを守り続けています。「この種は、祖父の祖父の代から守ってきた宝だ」。そんな言葉が聞こえてきそうです。
彼らの最大の心配は、GM作物の花粉が風で飛び、自分たちの畑のトウモロコシと交ざってしまうこと。もし交雑が進めば、伝統的な品種の特徴や味、色、香りといった“個性”が失われてしまいます。「種が交ざる=文化が消える」。そうした危機感が確かにあるのです。
一方、政府や一部の農業団体はGM作物の導入を「現代農業に欠かせない技術」だと位置づけています。
「害虫に強く、収穫量が増え、農薬の使用も減る」。実際、GMトウモロコシを使っている農家の中には、生産コストが2割近く下がったという報告もあり、これはあくまでワクチンを打った子どものようなものという意見も。
コロンビア政府内でも意見は真っ二つに分かれています。農業省は導入を推進する一方、環境省は「地域の食文化や生物多様性を守るべきだ」と慎重です。2025年6月には、ついに「遺伝子組換え種子の輸入と販売を禁止する法案」が議会に提出され、大きな波紋を呼びました。この動きは、アグリビジネス業界にとって大きな関心事です。種子や農薬を扱う多国籍企業は、「科学的根拠を無視した感情的な規制だ」と反発しています。もし禁止法案が通れば、企業の投資計画や契約が不安定になり、外国からの投資も減る可能性があります。
ただし、見方を変えれば「新しいビジネスチャンス」も見えてきます。世界的にオーガニック志向が高まる中、コロンビアの在来品種や非遺伝子組換え農産物は、ヨーロッパや日本市場で“安全で自然な食”として高く評価される可能性があるのです。
すでに一部の地域では、在来種を使った有機農業や、伝統的なトウモロコシ粉を使った商品ブランド化が始まっています。
実はこの問題、コロンビアだけの話ではありません。
お隣のペルーやエクアドルでは、すでにGM作物の栽培を禁止する「モラトリアム(猶予期間)」が設けられています。一方で、アルゼンチンやブラジルは、遺伝子組換え作物を積極的に輸出して外貨を稼いでいます。
つまり、南米は「GM推進派」と「自然派」に二分されているのです。
コロンビアがどちらの道を選ぶかは、地域全体の農業政策や国際取引にも影響します。もし「非GMの国」としてブランド化できれば、高価格市場へのアクセスが広がるかもしれません。逆に、禁止によって生産性が下がれば、輸入依存が進むリスクもあります。
GM作物をめぐる議論は、単なる技術論ではありません。
「誰が食料をつくり、誰がその権利を持つのか」
「私たちは何を食べて生きたいのか」
そんな問いを、コロンビア社会全体に投げかけています。
政府の政策、企業の利益、農家の誇り、そして消費者の価値観。
それぞれの立場が交錯する中で、コロンビアの農業は岐路に立っています。
畑の片隅で、今日もひとりの農夫が、自分の手で種を選び、土を耕しています。
その小さな手の中に、コロンビアの未来が握られているのかもしれません。