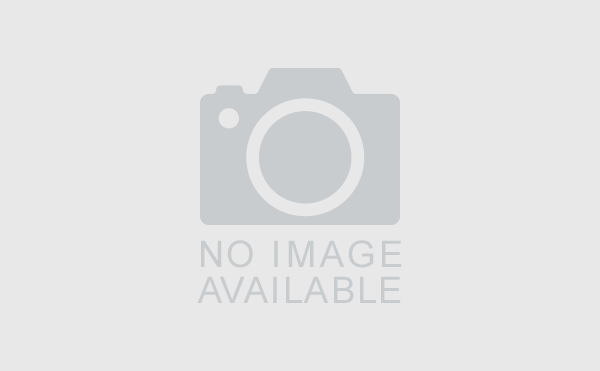コロンビアで揺れるGM作物論争について:伝統と生物多様性をめぐるビジネスの分岐点

コロンビアの農業界では、GM(遺伝子組み換え)作物をめぐる議論が「静かな戦争」のように深刻かつ戦略的に展開しています。これはただの技術導入の是非ではなく、文化、経済、国際競争力、食料主権、生物多様性という複数の軸が交錯した大きなビジネス問題です。
まず注目すべきは「種の守護者(Seed Guardians)」と呼ばれる小規模農家や先住民コミュニティの存在です。特にナリーニョ県などでは、彼らが伝統的な在来トウモロコシ品種を守る運動を続けており、単なる栽培材料以上に「種=文化」であるという認識があります。彼らはGM種子を強く警戒し、その導入が在来品種との交雑を引き起こし、生態的・文化的遺産を失うリスクを訴えています。
一方、商業農業やアグリビジネスの側では、GM作物の導入は競争力を高める重要な選択肢です。害虫耐性や除草剤耐性を持つGMトウモロコシは、収量の安定化に貢献し、農家にとってコスト削減や生産性向上の手段になるからです。大規模・中規模農家にとっては、GM技術は国際市場、特に家畜飼料向けや穀物市場での強みをつくるツールにもなり得ます。
しかしこの論争には具体的な数字も背後にあります。コロンビア農業機関(ICA)によれば、2023年には 15万4,677ヘクタール がGM作物で栽培され、これは過去最高を記録しました。
その内訳では、GMトウモロコシが 14万2,711ヘクタール を占め、前年から 20%増加。これは国内トウモロコシ全体の約 36% にあたり、GMコーンが急速に普及していることを示しています。
このGM作物の普及拡大は、政策の場でも激しい議論を巻き起こしています。2024年には、GM種子の国内規制あるいは禁止を求める法案が議会で提出されました。
この動きには、先住民団体、環境団体、農民組合などが賛同しており、食料主権(自分たちの種をどう管理するかを決める力)を守る闘いだと位置づけられています。
一方で、アグリバイオ(農業バイオテクノロジー)業界や一部科学者からは「技術を閉ざすのは生産性や食料安全保障を脅かす」との反論があり、議論は国としての方向性を問うものになっています。さらに重要なのは、生物多様性の損失という長期リスクです。コロンビアには少なくとも 23の在来トウモロコシ品種 が存在しており、地域ごとに適応したローカル品種が多様に残っています。
GM作物が広がることで交雑し、在来種が失われていくと、生態系としての強みや文化的資産が薄れてしまう可能性があります。これは、単なる農業の効率化以上の問題です。また、GM作物は必ずしも「大農家だけ」に恩恵をもたらすとは言えません。GM種子は特許があるものが多く、毎年購入が必要になる種類もあるため、小規模農家がそれを負担に感じる可能性があります。種の自家保存が難しくなれば、伝統農家は技術の恩恵を受けながらも依存を強めるリスクがあります。
一方で、アグリバイオ側はGM作物がコロンビアの食料輸入依存を下げる可能性を強調します。実際、報道によればコロンビアは年間に何百万トンもの食料を輸入しており、国内生産力を強化する戦略の一環としてGM技術を推進すべきだ、という主張があります。
彼らはまた、気候変動や病害虫への耐性を持つ作物を育てることで将来的なリスクに備えるべきだと論じています。
議会レベルでも、法案はまだ最終採決には至っておらず、8回の立法論議が必要だとされています。
つまり、コロンビアにとってはGM作物をどう扱うかが、農業戦略だけでなく、国家の農業ビジョンそのものの岐路になっているわけです。
この論争のビジネス的な意味は非常に大きいです。もしGM作物に対して強い規制が敷かれれば、コロンビアの輸出農業(特に大豆や穀物)は生産コストや技術の選択肢で制限を受ける可能性があります。逆に規制が緩和されてGMがさらに広がれば、小規模農家と在来種を守る運動との対立が深まり、生物多様性や文化価値を損なうリスクがあります。
最後に、この論争はコロンビアが目指す農業像を象徴しています。効率性と国際競争力を追う近代農業の道、あるいは伝統、自治、食の主権を守る道。どちらを選ぶかによって、コロンビアの未来の農業は大きく変わるでしょう。そしてその決断は、単なる農業技術の選択を超えて、社会、文化、そして国際市場での立ち位置を左右する重大な分岐点なのです。